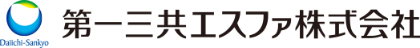不整脈の薬物治療
不整脈の治療には大きくわけて薬物治療と非薬物治療があります。薬物治療では服薬指導の際、患者さんに不整脈治療における薬物治療の役割や作用を伝えることで、患者さんの疾患理解が深まり、服薬アドヒアランスが向上します。

薬物治療の対象となる主な不整脈
不整脈の種類によって、薬物治療の適応や目的、使い方が異なります。また、薬物治療の対象となるのは主に頻脈性不整脈です(表1)。
表1 薬物治療の対象となる主な頻脈性不整脈
・ 心房細動
・ 心房粗動
・ 発作性上室性頻拍
・ 心室期外収縮
・ 心室頻拍
頻脈性不整脈は適切に治療しないと、生命に危険が及ぶことがあります。薬物治療を行う場合は、不整脈を抑えるとともに、合併症を防ぐことが使用するうえでのポイントになります。
徐脈性不整脈はペースメーカの植込みが行われることが多く、薬物治療の効果は限定的なものといわれています。そのため、薬物治療はペースメーカ植込み手術までの症状の緩和などを目的に、一時的に行われることが多いです。
心房細動についての解説はこちら
抗不整脈薬の分類と作用
抗不整脈薬には、主に各種イオンチャネルの修飾によって伝導障害や興奮の生成を制御する作用があります。分類としては、抗不整脈作用別のVaughan Williams分類※1(表2)、電気生理学的および心電図に対する作用を反映したSicilian Gambit※2、3の2つがあります。Sicilian Gambit には、Vaughan Williams分類で抗不整脈薬に含まれていないものも含みます。今なお、Vaughan Williams分類で考えるのが一般的となっています。
| 分類 | 作用 | 一般名 | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaughan Williams分類 | I群 | ナトリウムチャネル遮断 | ― | |
| IA群 | PR/QRS幅軽度延長 APD延長 |
キニジン硫酸塩水和物、プロカインアミド塩酸塩、ジソピラミド、ジソピラミドリン酸塩、シベンゾリンコハク酸塩、ピルメノール塩酸塩水和物 | ||
| IB群 | PR/QRS幅不変 APD短縮 |
リドカイン塩酸塩、メキシレチン塩酸塩、アプリンジン塩酸塩 | ||
| IC群 | PR/QRS幅中等度延長 APD不変 |
ピルシカイニド塩酸塩水和物、プロパフェノン塩酸塩、フレカイニド酢酸塩 | ||
| II群(β遮断薬) | 交感神経β受容体遮断 | カルベジロール、プロプラノロール塩酸塩、メトプロロール、ビソプロロールフマル酸塩 など | ||
| III群 | カリウムチャネル遮断 | アミオダロン塩酸塩、ソタロール塩酸塩、ニフェカラント塩酸塩 | ||
| IV群 | カルシウムチャネル遮断 | ベラパミル塩酸塩、ベプリジル塩酸塩水和物 、ジルチアゼム塩酸塩 | ||
| その他の抗不整脈薬 | ジギタリス | ジゴキシン、デスラノシド、メチルジゴキシン | ||
| ATP | アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 | |||
| アトロピン | アトロピン硫酸塩水和物、硫酸アトロピン | |||
※APD:活動電位持続時間(action potential duration)
薬剤の特徴
抗不整脈薬は、患者さんの病態に応じて拍動のリズムを安定させたり、症状を抑えて心拍数を調整したりする目的で使いわけられています。
●I群薬(IA~IC群:ナトリウムチャネル遮断薬)
I群薬は、洞結節や房室結節以外の心筋細胞でナトリウムチャネルに結合します。心筋細胞内へのナトリウムの流入を遮断することで、心筋細胞の電気興奮の発生を抑え、心房と心室で起こる旋回興奮を抑制します。主に、心房細動の抑制目的で使用されます。
IA群薬は、比較的強いカリウムチャネル遮断作用も併せもつため、活動電位持続時間が延長します。また、IC群はナトリウムチャネル遮断の強い作用と弱いカリウムチャネル遮断作用があり、その作用が相殺することで活動電位持続時間がほとんど変わりません。IB群にはカリウムチャネル遮断作用はなく、活動電位持続時間が短縮します。
注意すべき副作用
IB群は催不整脈作用が問題となることは少ないですが、IA群ではQT間隔の延長、IC群ではQRS間隔の延長によって新たな不整脈の発現リスクがあります。また、IA群とIC群では、心機能の低下を引き起こすリスクがあるため、心不全を伴った患者さんでは使用できません。そのほか、IA群では抗コリン作用による口渇、尿閉、眼圧の上昇などの副作用が発現することがあり、シベンゾリンコハク酸塩では糖尿病治療中の患者さんで低血糖が発現することがあります。
●II群薬(β遮断薬)
交感神経に作用することで抗不整脈作用を示す薬です。洞結節と房室結節は交感神経の支配が強いため、β遮断薬を投与すると心拍数が減少し、伝導が抑制されます。
β遮断薬は、洞結節における刺激生成の機能低下と房室結節における伝導遅延作用を有します。不整脈の減少効果は強くないものの、心房細動の心拍数コントロール、運動誘発性の不整脈や日中に起こる交感神経関与の期外収縮に対しては有効で、器質的心疾患や心不全を有する患者さんの心室性不整脈の発生を予防する効果もあります。
注意すべき副作用
催不整脈作用として、効果が強く出ることによって生じる徐脈や房室ブロックがあげられます。そのほか、心機能の低下や血圧の低下をもたらすリスクがあるため、少量から投与を開始して徐々に増量します。また、全身倦怠や睡眠障害、間歇性跛行、うつ傾向などの副作用があります。非選択性β受容体遮断作用薬では、気管支喘息を誘発することがあります。
●III群(カリウムチャネル遮断薬)
III群薬は、カリウムチャネルの遮断によって活動電位持続時間を延長させる薬剤です。心筋の興奮後の不応期が高度に延長することで、心房と心室の旋回興奮が抑制されます。カリウムチャネルの遮断作用は、心房よりも心室において強く出る傾向があるため、III群薬は主に心室頻拍の抑制目的で使用されます。
注意すべき副作用
催不整脈作用として、過度のQT延長に伴うトルサー・ド・ポアンツの発現があげられます。とくに低カリウム血症、低マグネシウム血症、心不全がある患者さん、女性の場合、QT延長作用がより強く出ることがあるため注意が必要です。このほか、アミオダロン塩酸塩では、間質性肺炎や甲状腺機能障害、肝障害、視神経炎の眼合併症、日光過敏症などの副作用があるため、薬剤師は事前の服薬指導で十分副作用について説明することが重要です。
●IV群(カルシウムチャネル遮断薬)
IV群薬は、カルシウムチャネルの遮断作用によって活動電位持続時間を延長させる薬剤です。非ジヒドロピリジン系のカルシウム拮抗薬がこれに含まれます。心筋の興奮後の不応期の延長作用に加えて、洞結節での刺激生成の機能低下や房室結節での比較的強い伝導遅延作用を有します。房室結節での伝導抑制作用を利用して、主に発作性上室頻拍の抑制目的で使用されます。
注意すべき副作用
催不整脈作用として、効果が強く出ることによって生じる徐脈、伝導を抑える作用による房室ブロックなどがあげられます。また、ベラパミル塩酸塩とジルチアゼム塩酸塩は心機能の低下をもたらすリスクがあるため、心不全を伴った患者さんでは投与できません。
●その他の抗不整脈薬
Vaughan Williams分類でI~IV群に含まれていない抗不整脈薬に、ジゴキシン、アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物(ATP)、アトロピン硫酸塩水和物があります。それぞれの特徴は表3のとおりです。
| 一般名 | 抗不整脈薬としての特徴 |
|---|---|
| ジゴキシン | 洞結節、房室結節での電気興奮の伝導を抑え、心拍数を抑制する。心筋収縮力の増強作用があるため、心不全を合併した心房細動や心房粗動などの心拍数コントロール目的に使われる
※ジギタリス中毒による催不整脈作用による心室期外収縮、心室頻拍、心室細動に注意が必要である |
| アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物(ATP) | 洞結節からの電気興奮の発生や房室結節での伝導抑制作用があり、急速に投与すると一過性に遮断することができる。発作性上室頻拍の治療に使われることが多い |
| アトロピン硫酸塩水和物 | 洞結節や房室結節での迷走神経抑制作用により、洞結節からの電気興奮および房室伝導を促進させ、心拍数を増加させる |
<文献>
| ※1 | Vaughan Wiliams EM. Classification of antiarrhythmic drugs. In: Snadoe E, Flensted-Jensen E, Olsen KH, editors. Symposium on cardiac arrhythmias, Elsinore,Denmark. Astra 1970: 449–472. |
| ※2 |
The Sicilian gambit. A new approach to the classification of antiarrhythmic drugs based on their actions on arrhythmogenic
mechanisms. Task Force of the Working Group on Arrhythmias of the European Society of Cardiology. Circulation 1991; 84: 1831–1851. PMID: 1717173 |
| ※3 | The ʻSicilian Gambitʼ. A new approach to the classification of antiarrhythmic drugs based on their actions on arrhythmogenic mechanisms. The Task Force of the Working Group on Arrhythmias of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 1991; 12: 1112–1131. PMID: 1723682 |
| ・ | 日本循環器学会・日本不整脈心電学会合同ガイドライン:2020年改訂版不整脈薬物治療ガイドライン
http://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2020/01/JCS2020_Ono.pdf (2023年9月29日閲覧) |
| ・ | 日本循環器学会・日本不整脈心電学会合同ガイドライン:2022年改訂版不整脈の診断とリスク評価に関するガイドライン
https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2022/03/JCS2022_Takase.pdf (2023年9月29日閲覧) |
| ・ | 厚生労働省:「家庭用心電計プログラム」及び「家庭用心拍数モニタプログラム」の適正使用について
https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/01/academyinfo20210129.pdf (2023年9月29日閲覧) |
| ・ | 池田隆徳監:いちばん親切な モニター心電図の読み方.新星出版社,2019. |
| ・ | 杉薫監:これで安心!不整脈〜脳梗塞・突然死を防ぐ.高橋書店,2013. |
| ・ | 池田隆徳:特集 不整脈:診断と治療の進歩 I.病態と診断の進歩 1.不整脈の種類と分類.日本内科学雑誌,日本内科学会,95(2):196−202,2006.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/95/2/95_2_196/_pdf (2023年9月29日閲覧) |
| ・ | 松田直樹:特集 不整脈:診断と治療の進歩 II.治療 3.不整脈の薬物療法の現状と展望 1)抗不整脈薬の分類と電気生理.日本内科学雑誌,日本内科学会,95(2):240−245,2006.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/95/2/95_2_240/_pdf (2023年9月29日閲覧) |
| ・ | 池田隆徳:2021年度日本内科学会生涯教育講演会Bセッション 不整脈に対するガイドラインに準じた治療戦略.日本内科学会雑誌,日本内科学会.111(3):511-518.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/naika/111/3/111_511/_pdf (2023年9月29日閲覧) |

東邦大学大学院医学研究科循環器内科学 教授
池田 隆徳先生
1986年東邦大学医学部卒業。東邦大学医学部第三内科助手、米国シーダス・サイナイ医療センター&UCLA留学を経て、2002年杏林大学医学部第二内科講師に就任。同大学助教授(准教授)、教授を務めた後、2011年東邦大学大学院医学研究科循環器内科学、同医学部内科学講座循環器内科学分野教授に就任。翌2012年に同大学医療センター大森病院循環器センター長に就任。2024年に同大学医学部長・大学院医学研究科長に就任し、現在に至る。国際ホルターノンインベイシブ学会理事長、国際心電学会常務理事、日本循環器学会理事、日本不整脈心電学会理事、日本心血管協会理事長、日本心臓病学会代議員、日本内科学会評議員、日本心血管脳卒中学会役員などを務める。専門分野は循環器内科学(不整脈・心電学)。
この記事は2024年8月現在の情報となります。