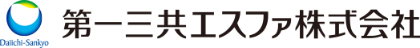心不全の治療
心不全の治療は、大きく急性期と慢性期にわかれます。急性期は緊急性が高く、救命や生命徴候の安定が優先されます。一方、慢性心不全は急性増悪を繰り返しながら徐々に進行していくもので、主な治療の目的は急性増悪の予防とQOLの維持です。

心不全治療の目標
心不全はステージによって治療目標が異なりますが、心不全発症後のステージC、Dでは心血管イベントを防ぎ、症状の軽減を図ることが主な治療目標となります(表1)※1)。
| ステージ | 治療目標 |
|---|---|
|
ステージC
(症候性心不全) |
予後の改善、心不全に伴う症状の軽減、QOLの改善によってステージDへの進行を防ぐ |
|
ステージD
(治療抵抗性心不全) |
適切な治療を受けていても症状が残り、心不全の急性増悪などによって入院を繰り返す。症状の軽減や予後改善のため、補助人工心臓や心臓移植などの治療のほか、緩和ケアを検討する |
ステージDに至ると、患者さんによっては生命予後の延長よりもQOLの維持・向上を優先する場合があります。患者さんには治療の選択肢とその判断材料となる正しい情報を提供したうえで、患者さんの意思決定を支援しましょう。患者さんの意思決定に基づいて、医療・介護サービスや地域の社会資源を活用しながら各職種が連携し、療養環境を整えます。
心不全治療のアルゴリズム
ステージC、Dの心不全治療は、どちらも多職種による栄養管理や心臓リハビリテーションなどの疾病管理、セルフケアの指導、緩和ケアなどの提供が基本となります。治療には、大きくわけて薬物療法と非薬物療法があります(図1)。
図1 心不全治療のアルゴリズム
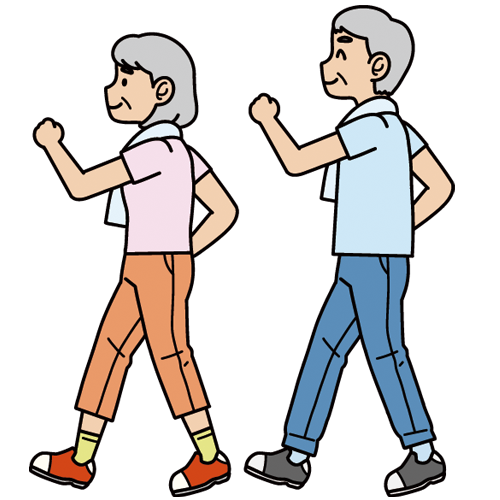
【出典】日本循環器学会/ 日本心不全学会.2025年改訂版心不全診療ガイドライン.
https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2025/03/JCS2025_Kato.pdf (2025年8月閲覧)
ICT:Implantable Cardioverter Defibrillator(植え込み型除細動器)
CRT:Cardiac Resynchronization Therapy(心臓再同期療法)
注)上記図1のガイドラインに記載されている*3と*4の一部薬剤については、保険適応外使用となります(2025年8月現在)。
BNP/NT-proBNPによる心不全管理
BNP/NT-proBNPは、診断のみならず心不全管理にも有用です。心不全患者さんのうっ血の早期発見、うっ血に対する治療の強化や心不全患者さんに対する薬物療法の最適化の指標としても使われています。
BNP/NT-proBNPについてはこちら
心不全の薬物療法
薬物療法は心不全治療の柱となるもので、ステージC、Dでは、LVEF(左室駆出率)に応じて薬剤を選択します※1)。心不全治療薬の選択肢が増えていることから、薬剤師が患者さんの病態と薬剤の特徴を丁寧に説明し、服薬アドヒアランス向上に努めることが重要です(表2、3)。
| 薬剤 | 特徴 |
|---|---|
| ACE阻害薬 |
・禁忌を除くすべての左室収縮機能低下がある心不全に生命予後改善効果を目的として投与する
・腎機能の低下とカリウム値に注意が必要 |
| ARB |
・左室収縮機能低下がある慢性心不全において、ACE阻害薬と同等の心血管イベント抑制効果がある
・副作用などによりACE阻害薬が使用できない患者さんに対して使われることが多い ・腎機能の低下とカリウム値に注意が必要 |
| ARNI |
・ARBのバルサルタンとネプリライシン阻害薬のプロドラッグを結合させたもので、強い心保護作用を得られる点が特徴
・ACE阻害薬やARBで十分な効果が得られなかった場合のHFrEFに対する選択肢となる |
| β遮断薬 |
・禁忌を除くすべての左室収縮機能低下がある心不全に対し、生命予後改善効果を期待して投与する
・徐脈、低血圧に注意 |
| MRA |
・左室収縮機能低下があり、ACE阻害薬・ARBまたはβ遮断薬などの基礎治療を受けているNYHA心機能分類II-IVの心不全患者さんに投与推奨
・腎機能の低下とカリウム値に注意が必要 |
| SGLT2阻害薬 |
・糖尿病の有無にかかわらず、症候性のHFrEFに対して、心血管死および心不全入院の抑制を目的として投与する
・高齢でフレイルの患者さんに対しては注意が必要であり、ループ利尿薬の調整を行う場合もある |
| イバブラジン塩酸塩 |
・β遮断薬投与にもかかわらず頻脈である洞調律のHFrEF患者さんに対して、心血管イベント抑制を目的として投与する
・心拍数を低下させることで心臓の拡張時間を確保して心臓に十分な血液を戻す効果が期待できる |
| ベルイシグアト |
・可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)を刺激することで心筋や血管機能を調節するcGMPの産生を促す
・十分なガイドライン推奨治療にもかかわらず心不全増悪をきたしたNYHA心機能分類II-IVのHFrEF患者さんに対して、心血管イベント抑制を目的として投与する |
| 利尿薬 |
・うっ血による労作時呼吸困難や浮腫などの症状軽減にループ利尿薬を用いる
・ループ利尿薬に抵抗性の場合、バソプレシンV2受容体拮抗薬の投与を考慮する |

| LVEF | 薬物療法 |
|---|---|
| HFrEF | RAS系阻害薬(ACE阻害薬、ARB、ARNI)、β遮断薬、MRA、SGLT2阻害薬の4種類の薬剤(Fantastic Four)を基本に、低用量から開始する。この4種類の薬剤はとくにHFrEFの治療で効果が期待できるもので、忍容性を確認しながら目標量まで増量する |
| HFmrEF | HFmrEFの場合はHFrEFからの移行だけでなく、HFpEFからの移行でHFmrEFに至っているケースもある。経過を慎重に評価しながら薬物療法を継続する |
| HFpEF | SGLT2阻害薬を中心に、併用薬としてARNI、ARB、MRAなどを使用する。HFpEFの患者さんは、高血圧や心房細動、冠動脈疾患、糖尿病、腎機能障害など複数の疾患を併発していることが多いため、心不全治療と並行して各併存疾患の管理を行うことが重要 |
心不全の非薬物療法
非薬物療法でとくに重要となるのが栄養管理と心臓リハビリテーションです。このほかの非薬物療法としてペースメーカーを用いた心臓再同期療法や心補助人工心臓の手術、心臓移植などがあります。
●栄養管理
心不全患者さんには定期的に栄養状態を評価したうえで、年齢や基礎代謝量、活動量などに応じた適切なエネルギー摂取量を設定します。栄養状態は、心不全を含めたこれまでの病歴、身長や体重、BMIなどの身体計測値、食習慣や食事内容、生化学検査、身体症状(浮腫や栄養素欠乏に関連する所見)、身体機能(呼吸機能や嚥下機能など)から評価します。薬剤師による患者さんへの指導では、食習慣をはじめ、服薬にも関連する嚥下機能の状態などについても聞き取り、必要に応じて主治医や看護師、管理栄養士と情報を共有します。

●低栄養にも注意が必要
低栄養と心不全は相互に悪影響をもたらすもので、予後の悪化につながります。ステージC以降の慢性心不全患者さんは、急性増悪を繰り返すなかで徐々に身体機能が低下し、栄養状態がさらに悪化したり、筋肉量が減少したりするため、フレイルリスクも高くなります。心不全患者さんの低栄養は、60~69%にのぼり、心血管イベントの発生率とも関連しているという報告があります※2)。
●心臓リハビリテーション
心臓リハビリテーションは、心不全のリスクが高い段階から、疾病管理と並ぶ非薬物療法の柱のひとつです。退院後は生命予後の延長、心不全の急性増悪・再入院の予防、ADL(日常生活動作)やQOL(生活の質)の維持、運動耐容能の改善・維持、生活・就労などを目的に心臓リハビリテーションを継続します。
患者さんの運動耐容能は個人差が大きいため、適切な運動耐容能の評価によって、医師が患者さんの運動処方を決定します。1回20~60分程度を目標に、徐々に運動の時間を延ばしたり、強度を上げたりします※3)。
そのほか、心不全が進行する原因となる基礎疾患の治療などを含めると、心不全に対する非薬物療法は多岐にわたるため、医療従事者による患者さんや家族への正しい情報提供が重要となります。薬剤師が主に関わるのは薬物療法ですが、非薬物療法に対しても必要なときに説明できるように、日ごろからの情報収集を心がけましょう。
<文献>
| ※1) |
日本循環器学会/日本心不全学会:2025年改訂版 心不全診療ガイドライン.
https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2025/03/JCS2025_Kato.pdf (2025年7月3日閲覧) |
| ※2) |
Narumi T, Arimoto T funayama A, et al: Prognostic importance of objective nutritional indexes in patients with chronic heart failure. J cardol 62: 307-313, 2023. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23806549/ (2025年7月3日閲覧) |
| ※3) |
日本循環器学会/日本心臓リハビリテーション学会: 2021年改訂版心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン.
https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/JCS2021_Makita.pdf (2025年7月3日閲覧) |
| ・ | 筒井裕之編:ザ・ベーシックメソッド心不全薬物治療 知識を習得し、実践で活かす最強のメソッド.メジカルビュー社,2021. |
| ・ | 木田圭亮:聞いてみよう薬剤師の知りたいこと 心不全の最新ガイドラインをキャッチアップ!知っておきた新薬のハナシ.調剤と情報,28(1):58-64,2022. |
| ・ | 大八木秀和:オールカラーまるごと図解循環器疾患.照林社,2013. |
| ・ | 佐藤幸人:特集 心血管疾患の栄養管理 識る5 心不全進展ステージに応じた栄養管理の考え方.Heart View,27(4):28-33,2023. |
| ・ | 肥後太基:特集 心血管疾患の栄養管理 治す10 慢性心不全における低栄養への介入.Heart View,27(4):56-63,2023. |
| ・ | 絹川真太郎:特集 心不全の心臓リハビリテーション―進行を抑えQOL・症状を改善する治療法― 治す9 ステージCの心臓リハビリテーション.Heart View,24(6):56−62,2020. |
| ・ | 簗瀬正伸:特集 心不全の心臓リハビリテーション―進行を抑えQOL・症状を改善する治療法― 治す10 ステージDの心臓リハビリテーション.Heart View,24(6):63−67,2020. |

兵庫県立尼崎総合医療センター循環器内科科長/副院長
佐藤 幸人先生
1987年京都大学医学部卒業。94年同大大学院卒業。2001年京都大学循環器内科助手、04年兵庫県立尼崎病院循環器内科医長、07年同科部長、23年より現職。研究テーマは心不全、バイオマーカー、チーム医療など。
この記事は2025年7月現在の情報となります。